6歳・8歳の息子を持つママライター、永野栄里子です。
小学校に上がると、日々の宿題や自主学習で、自宅での勉強シーンが増えてきます。小学生の勉強時間は、どれくらい確保するとよいのか悩む保護者も多いのではないでしょうか。
今回は、小学生の勉強時間の目安や実際の平均時間を紹介します。習慣化させるポイントにも触れているので、中学・高校に向けた家庭学習定着の参考にしていただければ幸いです。
小学生の勉強時間の目安

小学生といっても、1年生と6年生では学習内容や子どもの成長も異なります。勉強時間を決める1つの目安は、「学年×10分~15分」といわれています。
1.2年生の勉強時間の目安
前述の式に当てはめると、1年生の勉強時間の目安は「1×10~15」で、10分~15分程度です。宿題以外の自主学習をする場合は、10分ほどでも問題ありません。
大人にとっては「短すぎる」と感じるかもしれませんが、1年生になったばかりの頃は勉強内容も比較的簡単です。まずは、毎日机に向かう学習習慣を身につけることを優先しましょう。
2年生になると「2×10~15」で、20~30分程度が目安になります。2年生は1年生よりも学習内容がやや複雑になり、算数では九九や2ケタの足し算・引き算、国語はより難しい漢字を習います。
宿題が多い場合は、プラスアルファの学習を考えるよりも、毎日丁寧に宿題をこなすことを考えましょう。宿題が少ないときには、15~20分程度の自主学習も取り入れるのがおすすめです。
3.4年生の勉強時間の目安
3年生の勉強時間の目安は「3×10~15」で、30~45分程度となります。3年生になると理科・社会が新たな学習強化として追加され、学校によってはより本格的な英語の授業も導入されることがあります。
4年生は「4×10~15」で、40分から1時間程度の勉強時間が目安です。1.2年生よりも集中力がつき、長い時間机に向かっていられる子どもも増えてきます。
3年生は高学年に向けての準備、4年生は5.6年生になったときにさらに長時間勉強することを踏まえ、徐々に勉強時間を長くしていくとよいでしょう。
5.6年生の勉強時間の目安
5年生の勉強時間の目安は「5×10~15」で、50分から1時間15分、6年生は「6×10~15」で、1時間から1時間半です。学年が上がりさらに学習内容が難しくなりますし、宿題も増えます。
宿題が多いと、それだけで1時間近くかかってしまうこともあるでしょうが、30分程度で終わる場合は中学校に進学したときのことを踏まえ、プラスアルファの学習を取り入れていくとよいでしょう。
しかし、なかには集中力が続かない子どももいます。集中できていない状態で勉強をしても、効率的な学習は実現できません。「20分ごとに休憩をはさむ」「宿題は帰宅後、自主学習は夕飯のあと」など、学習時間を細かくわけて取り組むのも1つの方法です。
小学生の勉強時間はどのくらい? その目安と学習の習慣づけのためにできること(https://www.889100.com/column/column105.html)
小学生の家庭学習、平均時間は?
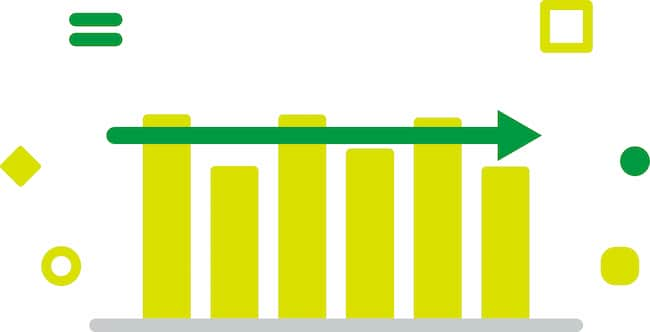
小学生の勉強時間の目安は前述の通りで、学年によってその長さは異なります。では、実際に日々子どもたちはどれくらい自宅で勉強しているのでしょうか? 平均時間を見てみましょう。
低学年の平均勉強時間
2022年に東京大学社会科学研究所とベネッセ教育研究所が実施した「子どもの生活と学びに関する親子調査」によると、低学年(小1~3)の平均勉強時間は48分でした。また、少し古いデータではありますが、学研教育総合研究所が2014年に実施した「小学生の日常生活に関する調査」では、小学校1~3年生までの勉強時間の平均は、約60分となっています。

上図は、「宿題を含めて、家での勉強時間を教えてください」という質問に対する回答です。1年生で最も多かったのは30分以下で、なかには10分、15分ほどという子どももいるでしょう。しかし平均は51分で、1時間以上勉強している子どもも多いことがわかります。
2.3年生になると、1時間以上勉強する子どもはさらに増えます。
高学年の平均勉強時間
「子どもの生活と学びに関する親子調査」では、高学年(小4~6)の平均勉強時間は78分(1時間18分)で、低学年よりも30分も長くなっています。また、「小学生の日常生活に関する調査」から見た平均時間は77.3分(約1時間17分)で、2014年から2022年にかけて、高学年の勉強時間に大きな変化がないことがわかります。
2014年の調査では、高学年になっても勉強時間が30分以下と回答した割合は2割程度でした。1時間が最も多いですが、6年生は全体の44%が1時間半以上勉強しています。
2つの調査から、学年にかかわらず、小学生は目安となる時間以上に勉強していることがわかるでしょう。
小学生の勉強を習慣にする6つの方法は? 学年別勉強時間やおすすめ勉強法も(https://benesse.jp/contents/1nensei/gakushu/article1.html)
小学生白書Web版・2014年9月調査(https://www.gakken.jp/kyouikusouken/whitepaper/201409/chapter4/09.html)
短時間でも低学年から勉強を習慣づけしたほうがよい?

平均時間を見てわかるように、低学年のうちから比較的長い時間勉強している子どもは多いです。「1時間も座っていられない」「平日は仕事があって自主学習を見てあげられない」という場合も、低学年のうちから勉強を習慣づけしたほうがよいといえます。
大きな理由の1つが、高学年の学習にスムーズに入っていくためです。小学校3年生になると理科・社会が始まり、4年生になると学習の難易度は大きく上がります。この時期、学習面で大きなストレスを抱える子どもは少なくありません。
低学年の頃から短時間でも家庭での学習に取り組んでいれば、「授業についていけない」というリスクを低減できます。塾や通信教育、市販の教材などでプラスアルファの学習をするのが難しい場合も、宿題のなかで「何が苦手か」「なぜわからないか」を理解して克服できれば土台ができ、次のステップにスムーズに上がっていけるでしょう。
小学生でも勉強させた方がいいの?習慣づけのコツと学習環境の大切さ(https://kagu.koizumi.co.jp/desk-column/3597/)
小学生の勉強時間はいつ確保する?

小学生の勉強習慣をつけるなら、できるだけ毎日同じ時間に取り組むのがおすすめです。子どもが集中しやすい時間はもちろん、学年が低いうちは保護者も見守りやすい時間帯を選ぶと、お互いの負担を軽減させながら、家庭学習を定着しやすいでしょう。
登校前
早起きが苦ではない子どもは、朝起きてから学校へ行くまでの時間に勉強するのがおすすめです。帰宅後は習い事で忙しいという場合も、登校前の学習は時間に余裕を持って行えるので気持ちにゆとりができます。
朝勉強すると脳が勉強モードになり、学校へ行っても集中して授業を受けられるのもメリットです。早寝早起きの習慣も身につき、一石二鳥でしょう。
帰宅後
帰宅してすぐに勉強すると、学校モードのまま取り組めるのが魅力です。宿題は授業の復習なので、頭に入った情報が新しいうちに取りかかれば、学習内容の定着にもつながるでしょう。
「宿題をしてからゲーム」「勉強が終わったらおやつ」など、ルールを決めやすいのもこの時間帯です。1日学校で過ごし、歩いて帰ってきてすぐに勉強するのは子どもにとっては大変かもしれませんが、早い段階で習慣化すれば成長してからもよい習慣として継続できます。
就寝前
帰宅後すぐに習い事がある場合は、用事やお風呂、食事などを済ませて就寝前に勉強するのもよいでしょう。就寝前は保護者が在宅している確率も高く、子どもは大人のいる環境で安心しながら勉強できます。
つきっきりで見守る必要はなく、隣で読書や仕事など、用事を済ませながら、わからない問題に対応すると、保護者も「勉強を見なければいけない」というストレスを感じにくいです。
習い事や仕事などで時間帯が不規則になってしまう場合は、「○曜日は何時から」「週末はこうしよう」と、柔軟に対応することも大切です。子ども、そして家庭全体のスケジュールやサイクルに合わせて、最適な学習時間を設定しましょう。
【小学生の家庭学習】勉強時間目安を学年別に紹介!楽しく習慣化するコツ(https://www.gakken.jp/homestudy-support/edu-info/%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E5%AD%A6%E7%BF%92/19996/)
小学生の家庭学習を習慣化させるためのポイント

小学生の家庭学習を定着させるには、保護者が工夫を凝らすことも大切です。最後に、最適な勉強時間を日々確保するためのポイントを解説します。
学習環境を整える
まずは、子どもが勉強に集中できる環境を整えることから始めましょう。机の上にマンガやおもちゃ、ゲーム機など学習に必要ないものを置いていないか、リビング学習の場合、テレビはつけっぱなしになっていないかなどに注目し、子どもが勉強と向き合える空間を作ります。
勉強時間が長くても、集中していなくては意味がありません。短時間でも集中して身になる学習を実現できれば、子どもは「勉強は面倒なもの」だと感じにくくなります。
子どもに合った教材を選ぶ
宿題以外にプラスアルファの学習を取り入れたい場合は、子どもの学習レベルに合った教材を選びましょう。いくら評判のよい教材でも、子どもが「簡単すぎてつまらない」「難しすぎてやる気をなくす」というものでは、あまり意味がありません。
家庭学習は、1人ひとりに合った内容やレベルを選択できるのがメリットですので、「苦手を克服するために、単元を絞ったドリル」「基礎を理解・定着させるためのワーク」「ワンランク上の学習を実現するための問題集」など、理解度に合ったものを選択してください。
ゲーム感覚で取り組めるタブレット学習を取り入れるのも、1つの方法です。
決まった時間に勉強する
前述の通り、子どもの習い事や保護者の仕事のスケジュールなども踏まえ、ルーティンを決めるのも有効です。「月曜日は習い事がないから帰宅後すぐ」「火~木曜日は習い事を済ませ、夕飯までのあいだ」といったように、大まかなルーティンを決めておくと、子どもも動きやすくなります。
スケジュールは親子で相談し、子どもの無理のないように行うことも重要です。「習い事のある日は宿題だけ」「その他の日は長めに学習時間を確保する」など、学習への意欲やレベルに合わせた計画をすると、毎日机に向かう習慣ができるでしょう。
タイマーを使う
学習時間の終わりがわからないと集中力が低下し、ダラダラとしてしまうこともあるので、タイマーを活用するのもおすすめです。10分、15分など決まった時間で設定し、アラームが鳴ったら休憩し、その後また学習に取り組むといったサイクルができると、集中力を持続しやすくなります。
時間を区切って取り組むことが「ゲーム感覚で楽しい」と感じる子どもには、特に高い効果を発揮するでしょう。
目標を決める
勉強には終わりがなく、1つの単元が終わればまた新しい学習内容に入り、子どもはその目的がわからなくなることもあります。親子で勉強する理由や目的を話し合うと、「なぜ勉強するのか」「将来役に立たないのではないか」といった、子どもの抱えるモヤモヤを解消し、学習習慣を身につけやすくなります。
また、大まかでもよいので目標を決めるのもよいでしょう。たとえば、「九九を早くいえるようになりたい」「1年間で習った漢字を完璧にしたい」といった小さな目標でもかまいません。「ドリルを○月までに1回終わらせる」「○○中学校を受験したい」「将来○○になりたいからそのために勉強する」など、具体的なものから大きなものまで、どのような目標でもよいので決めておくと、子どもも取り組みやすいでしょう。
保護者が声かけをする
保護者が家庭学習を促す声かけは大切ですが、その方法にも工夫しましょう。「勉強しなさい」と頭ごなしにいうと「いまやろうと思っていた」と、子どもは不満に思うこともあります。「今日の宿題は何?」「何を習ってきたの?」と、学習に意識を向けさせ、勉強が終わったら「どこまでできた?」「どんな学びがあった?」と、振り返りをし、頑張りを褒めることも大切です。
保護者の一言が子どものやる気を左右する部分も大きいので、励みになる言葉、うれしくなる言葉を選び、勉強への抵抗感をなくしてあげましょう。
小学生の学習時間は学年によって違う!低学年から取り組み習慣化させよう

小学生の勉強時間の目安は「学年×10~15分」ですが、実際にはそれ以上に勉強している子どものほうが多い傾向です。家庭での勉強習慣が早いうちに身につけば、中学・高校に進学して「受験」に直面した際にも、コツコツ努力しやすいといえます。
わが家では、私の仕事部屋に子どもの勉強机を置いて、帰宅しておやつを食べたら宿題と進研ゼミをするのが習慣です。次男は声をかけながらできる自主学習に取り組んでいますが、長男は「1週間でこれだけやる」というプラスアルファの課題を決め、自分で習い事とのバランスを考えて勉強しています。
勉強時間は日によって異なりますが、以前に字が汚すぎることと慌てて進めることによるケアレスミスが多いことを注意してからは「早く、乱雑に終わらせる」のではなく、「丁寧に書くこと」「問題をしっかり読むこと」を意識しています(が、まだミスは多いです)。
息子たちの勉強を見守るなかで、子どもの苦手な部分を理解し、改善・克服に向けた対策や声かけをすることも、保護者の重要な役割だなと感じます。大人も子どもも忙しい現代ですが、世の中の保護者の皆さんは、小学生の勉強を習慣化させるために一緒にがんばりましょう。



